最新フッ素関連トピックス」はダイキン工業株式会社ファインケミカル部のご好意により、ダイキン工業ホームページのWEBマガジンに掲載された内容を紹介しています。ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。尚、WEBマガジンのURLは下記の通りです。
http://www.daikin.co.jp/chm/products/fine/backnum/201405/
1、はじめに
フッ素系農薬は、F原子あるいはCF3基を含有するもので、フッ素のミミック効果、脂溶性、電気陰性度、C-F結合の強さなどの特徴が複合的に効いて、特異な薬効、薬剤の省資源化などにつながり、今では30%がフッ素系であるといわれる。下記に示すようにこの1年の化学工業日報記事に登場したフッ素系農薬は十数種あり、また、月刊ファインケミカル3月号の特集にも掲載されているように次々に新規なものが開発されている感がある。ここでは、新聞紙上に登場した十数種のフッ素系農薬を示し、さらにフッ素系農薬に関する最新の文献を紹介する。
2、この1年に新聞紙上に登場したフッ素系農薬と2013年日本で商品化された主要合成農薬
下記に2013年から今日までの化学工業日報に登場したフッ素系農薬とその化学構造を示す。
まずは、除草剤で最も多い。インダジフラム、ピロキサスルホン、フルミオキサジンはそれぞれ順に下記の構造を有する。
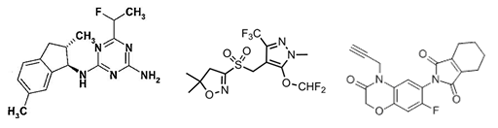
次いで、イブフェンカルバゾン、ベノキススラム、ピリミスルファンを示す。
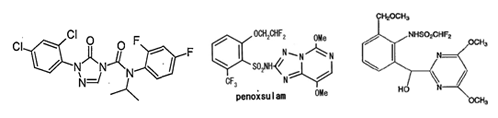
さらに、フルセトスルフロン、ベントキサゾンを示す。
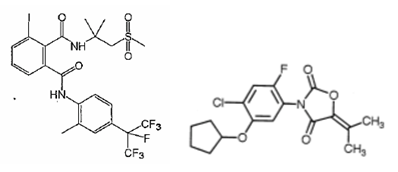
次に殺虫剤として、ピリフルキナゾン、フルベンズアミド、ビタバスタチンカルシウム、オルソスルファムロンが掲載された。それぞれ順に構造を示す。
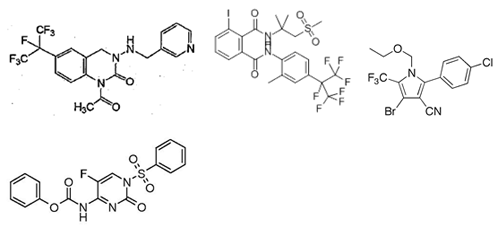
さらに、殺菌剤としてフルチアニルが掲載されていた。構造は下図の通り。
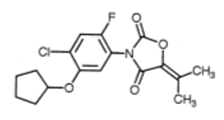
このうち、除草剤インダジフラム、ピロキサスルホン、イブフェンカルバゾン、ベノキススラム、ベントキサゾン、殺虫剤オルソスルファムロン、殺菌剤フルチアニルはこの1年間に登録、あるいは販売開始した農薬である。
3、文献情報
月刊ファインケミカルに2013年度に日本で上市された主要合成農薬がまとめられている。その中でフッ素系農薬は、上記の除草剤インダジフラム、殺菌剤フルチアニルが掲載されていた。また、開発中の農薬としては、ピロキサスルホンなどの除草剤17種、殺菌剤12種、殺虫剤7種のフッ素系農薬が提示されていた。1)
2006年にG.Theodoridisが、含フッ素農薬についての総説を書いている。2)その中で、農薬にフッ素を導入すると、目標レセプターや酵素への結合能力、農薬分子の目標サイトへの移動性などが改善され、フッ素系農薬はこの30年間で3倍に増えたと記している。
F. R. Lerouxらは、活性な農薬成分として含フッ素ピラゾールについての総説を発表している。3)含フッ素ピラゾールは、下図に示すSDHI剤(コハク酸脱水素酵素に作用して菌の呼吸を阻害する)の原料である。
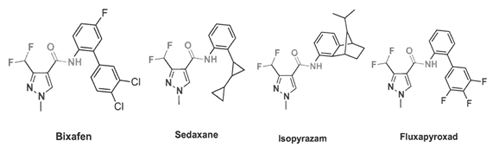
その合成法について、下図に示す多彩な原料からの合成法が述べられている。
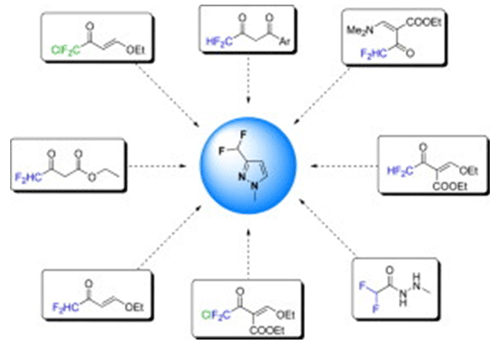
Jun-Biao Changらは、新規な殺ダニ剤であるpyriminostrobinをさらにフッ素化して下図の7eとすると生理活性が増大し、ニセナミハダニに対して0.625mg/Lでコントロールでき、殺虫剤としての能力はpyriminostrobinより優れているとしている。4)
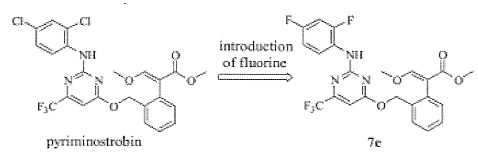
Bard Helge Hoffらは、フッ素化アリールエタノールをビルディングブロックとした生理活性物質についてのレビューを報告している。(下図のR1がCF3)5)
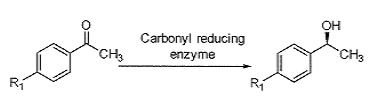
ここで、ケトンの還元でアルコール合成を行っているが、フッ素系の場合、触媒としては酵素触媒(抗利尿ホルモンADHなど)が効果的で、特に立体選択性が高いとしている。その中で、下記に示す殺虫剤XXVIや農業用抗真菌薬MA-20565 が紹介されている。
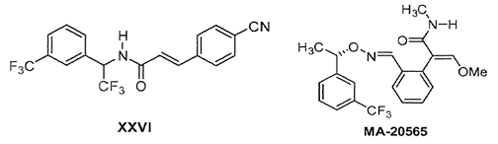
プロトポルフィリノゲン酸化酵素を抑制することは除草剤の開発につながる。Yang Guang-Fuらは、下図の化合物を26種類合成し、X=F、R=CH2COOC2H5(2e)およびX=F、R=CH(CH3)COOC2H5(2f)が最もプロトポルフィリノゲン酸化酵素の抑制効果が高いことを確認し、除草剤としては2fが最も高い活性を示したことを報告している。6)
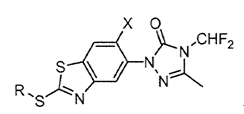
4、おわりに
フッ素系農薬は、新聞紙上にも頻繁に紹介され、月刊ファインケミカルに紹介されていた2013年度の農薬の中で半数以上はフッ素系であった。さらに2006年の総説でも30年間に3倍に増加していることが記述されており、その後も農薬の成分である含フッ素ピラゾールの総説をはじめとして、多くの報告がなされていて、環境問題が厳しく叫ばれる中で、益々その重要性を増していることは確実のようである。
文献
1) 月刊ファインケミカル シーエムシー 2014年3月号 p
2) George Theodoridis Advances in Fluorine Science, Volume 2, 2006, p121-175
3) Frederic R. Leroux et al Journal of Fluorine Chemistry152(2013) 2-11
4) Jun-Biao Chang et alChinese Chemical Letters 25(2014)137-140
5) Bard Helge Hoff et al Bioorganic Chemistry 51(2013) 31-47
6) Yang Guang-Fu et al Bioorganic & Medicinal Chemistry 21(2013) 3245-3253